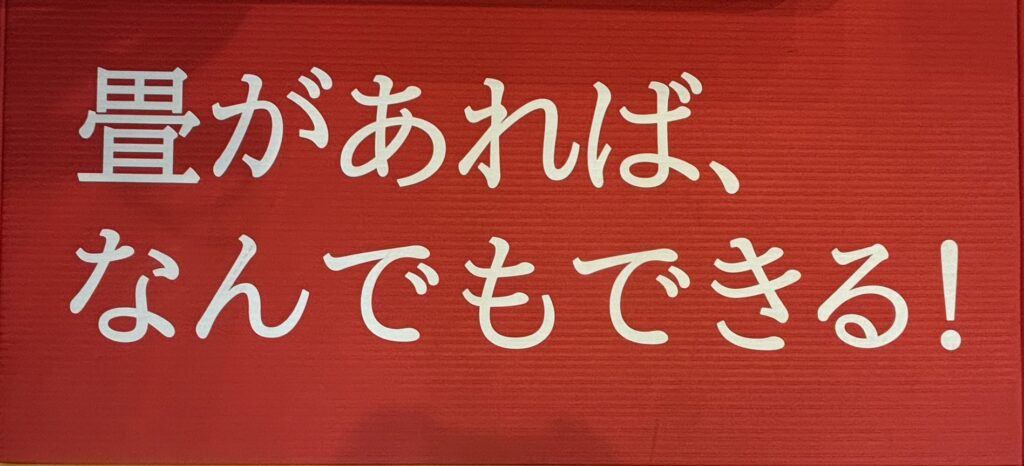
畳が変われば、柔道がもっと楽しくなる!
💬はじめに
選手たちは、畳に上がる前に一礼をします。
その一礼は、畳への敬意のあらわれ。
畳は、柔道の原点であり、土台であり、舞台です。
けれど今、私たちはその畳にどれだけ向き合えているでしょうか?
🧹現場の現実
練習後のほうきがけ。モップでの拭き掃除。
年に数回の畳上げ。
いまだ浸透しきらない掃除機がけ――
全柔連が推奨を始めても、日常のルーティンとして定着しているとは言い難いのが現状です。
畳に血がつけば、アルコールとトイレットペーパーで軽く拭き取る。それで「ひとまずきれいになった」と、安心してしまってはいませんか?見えない血痕がたくさん付着し残っています。
その一方で、毎日のように
汗、皮脂、唾液、血が畳の上に落ち、
道着や素足、手足で無意識のうちに擦り広げられています。
結果として、黒ずみや黄ばみ、臭いの染みついた道着。
それを“隠すように”強い柔軟剤の香りでごまかすような空気感が、柔道界に当たり前のように漂っています。
さらに、廊下やトイレから裸足で戻り、
入口の濡れた雑巾を踏んでそのまま畳に上がる――
こうした光景も、多くの道場で日常的に見られる“無意識のルーティン”になっています。
🧼衛生教育の盲点
そして、もっと深刻なのは、
「誰も掃除のやり方をきちんと教わっていない」ということです。
そのほうき、いつから使っているものですか?
掃除機の吸い取り口の裏は、どれだけの汚れがこびりついていますか?
ちりとりの縁に固まったゴミ、
ゴミ箱の底に残ったままの液体の汚れ――
見て見ぬふりをしていませんか?
ほうきの先には髪の毛や埃が絡まり、
掃除しているつもりが“汚れを広げているだけ”になっていることもあります。
掃除機の裏には黒ずみと臭いの元。
ちりとりの中にはこびりついたゴミ。
ゴミ箱の底はいつから洗っていないか分からない――そんな道場も少なくありません。
それらは、誰かにきちんと教わったものではなく、
“歴代の先輩から先輩へ”、なんとなく受け継がれてきた習慣なのです。
清掃は本来、「安全・衛生・礼の文化」の一環であるはずが、
ただの“片付け”になってしまってはいないでしょうか。
🔁変化の連鎖
畳を磨けば、道場が変わる。
道場が変われば、道着が替わる。
道着が替われば、選手が変わる。
選手が変われば、柔道が変わる。
柔道が変われば、未来は変わる。
それは、私たちの揺るぎない信念です。
🪞最後に
畳は、柔道界の鏡です。
その鏡を、プロの手で丁寧に磨く。
それが、TTPたにぐち畳ポリッシュの使命です。
畳に映る未来を変えるために、
今、畳に“新しい常識”を。
私たちは、畳を磨くことで、柔道場を守り、未来をつくります。
TTP:徹底的にPolish! ― それは、清潔・安全・感謝の心を磨く合言葉です。